2024年度、障害年金の審査で「不支給」と判定された人数が前年度の2倍以上に急増し、約3万人に達しました。単なる一時的な増減ではなく、制度運用そのものに根本的な“質的変化”が起きていると考えられます。
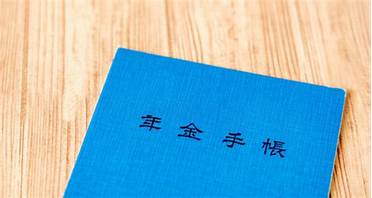
障害年金審査に何が起きているのか? 〜社労士や相談現場が感じている違和感〜
全国の社会保険労務士(社労士)や障害者支援団体、相談支援専門員たちの声を集めると、2024年度以降で、以下のような傾向が明確に見られます。
- 明らかに等級が下げられる、あるいは不支給となるケースが増加
- 以前なら2級が認定されていたケースでも3級や不支給と判断される
- 審査側の“裏取り”(確認調査)が増加し、診断書の内容だけでは不十分とされる傾向
このような傾向は、単に数が増えただけではなく、障害年金制度の運用の仕方、つまり審査基準の“質”そのものが変わった可能性を示しています。
支給されない理由:食事が摂れる、薬を飲んでいない?
審査現場では、信じがたいような理由で不支給や等級落ちがされるケースも報告されています。
- 「自力で食事を摂れている」→ 日常生活に重大な支障がないと判断
- 「薬を服用していない」→ 症状が安定していると見なされている
- 「主治医の診断書の記載が抽象的」→ 審査側が信用せず、不利な判断
実際には、精神障害の方が薬をやめたのは副作用や体調不良が原因であったり、認知障害の方が「食事は摂れる」が「火も包丁も使えない」といった生活実態があったりします。でも、「できている」と判断されてしまうのです。
増える“裏取り”と、主治医とのギャップ
また最近では、診断書に書かれた内容だけでは足りず、電話確認や家庭訪問、職場・学校への照会など、事実確認(裏取り)が頻繁に行われています。これにより、主治医が「日常生活に困難あり」と判断しても、実際の行動や第三者の意見が異なれば、診断書が否定されてしまうこともあります。
結果、「本当に困っている人が救われない」という矛盾が起きています。
制度が“排除のロジック”に傾きつつある危うさ
本来、障害年金は生活や就労に困難を抱える人を支えるための制度であるが、現在のような運用が続けば、支給されるべき人々が“目に見えない理由”で排除されてしまいます。
- 支援者の声が届かない
- 本人の困りごとが評価されていない
これでは、制度が「支えるため」ではなく「落とすため」に機能しているとも言えてしまいます。
まとめ
- 2024年度、障害年金の不支給が過去最多に
- 審査基準の“質的変化”が起きている可能性
- 社労士や相談現場では、診断書を超えた“裏取り”審査の強化を実感
- 制度が本来の「支え合いのための仕組み」から外れつつある懸念
この問題は、制度に携わる者だけでなく、すべての国民に関係する「社会保障のあり方」の問題でもあります。今後も注視する必要があるでしょう。
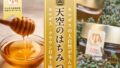
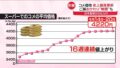
コメント