はじめに
最近よく耳にするようになった「マイナ保険証」。
これは、マイナンバーカードを健康保険証として使う仕組みのことです。
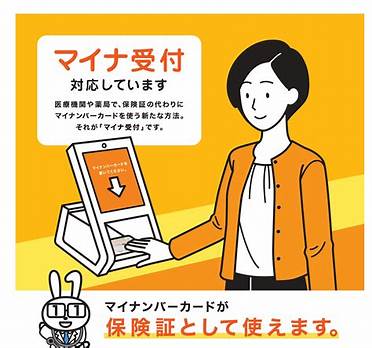
政府は「これからはマイナ保険証を使っていきましょう!」と推進していますが、実は現場ではいろんなトラブルが起きていて、利用している人はまだごく一部。
今回は、「マイナ保険証ってなに?」「なぜトラブルが多いの?」という疑問にやさしくお答えします。
マイナ保険証ってどんなもの?
マイナ保険証は、マイナンバーカードを病院や薬局で保険証として使うものです。
カードを専用の読み取り機にピッとかざすだけで、保険情報が確認できるようになっています。
本来なら、「紙の保険証を持ち歩かなくてOK」「本人確認がスムーズになる」など、便利なはずの仕組みです。
現在の利用率はたったの28%
でも実際には、2024年4月の時点で、マイナ保険証の利用率は28.65%。
つまり、10人中7人以上がまだ紙の保険証を使っているんです。
「使い方がよく分からない」「カードリーダーがちゃんと動かない」など、さまざまな理由で利用が進んでいないのが現状です。
医療現場ではトラブル続出
全国保険医団体連合会(保団連)が2025年5月に出した調査によると、全国9741の医療機関のうち、約9割がマイナ保険証で何かしらのトラブルを経験しているとのこと。
具体的には…
- カードを読み込めない
- 読み取った情報が文字化けする
- 有効期限が切れていて使えなかった
といったケースが多数報告されています。
特に最近は「有効期限切れ」が急増しているのが問題です。
「有効期限切れ」ってどういうこと?
ここが少し分かりにくいポイントになります。
マイナンバーカード自体の有効期限とは別に、「マイナ保険証として使うための設定(連携)」にも期限があります。
この期限が切れてしまうと、たとえマイナンバーカードを持っていても、保険証としては使えなくなってしまうんです。
でも、そのことに気づかず病院に行って、「あれ?使えない…」と慌てる人が多いのが現状です。
現場の声:「かえって面倒になっている」
医療機関の側からも、こんな声があがっています。
- 「読み取れず、紙の保険証を再提出してもらった」
- 「受付で説明が長くなり、診察が遅れる」
- 「特に高齢の患者さんが戸惑っている」
マイナ保険証は「便利になるはず」でしたが、実際はかえって時間がかかってしまっているというのが本音のようです。
政府の対応は?
政府もこの状況を問題視し、いろいろと対策を打ち出しています。
- 医療機関向けの補助金(カードリーダーの導入費など)
- カードリーダーの改良
- 国民への周知・広報活動
でも、制度自体が分かりにくいままではトラブルはなくなりません。
特に、「連携の有効期限」など、見落とされやすい部分のフォローが求められています。
今後どうなる?保険証は本当に無くなるの?
政府は、2026年中に現行の保険証を原則廃止する方針を出しています。
つまり、今のうちにマイナンバーカードと保険証の連携を済ませておかないと、将来困る可能性があるということです。
ただし、いきなり完全に切り替えるのは現実的ではないという声も多く、段階的な移行や例外措置も検討されているようです。
まとめ:便利さの裏にある“分かりにくさ”
マイナ保険証は、将来的には医療の効率化に役立つ可能性を持った仕組みです。
でも、今はまだ「便利」とは言えない面も多く、使い方や仕組みが分かりづらいのが最大の課題。
私たちとしては、慌てず、でも必要な手続き(連携の確認など)を今のうちにしておくことが大切です。
「マイナ保険証、ちゃんと使えるようになってるかな?」と、一度チェックしてみてはいかがでしょうか?


コメント