はじめに
2025年6月27日、厚生労働省が重要な方針転換を示しました。最高裁が過去の生活保護費引き下げを「違法」と断じた判決を受け、厚労省は減額分の追加支給を検討し始めたのです。
その対象は原告だけでなく、全国の受給者全体に広がる可能性があり、必要な財源は数千億円規模に上ると見られています。
なぜこうした事態に至ったのか? 本記事では、以下の5つの観点から今回の動きの背景と今後の展望を読み解きます。
1. 生活保護費引き下げの経緯とは?
2013年、当時の民主党から政権を奪取した自民党政権が、生活保護費の「生活扶助(主に食費・光熱費)」部分の見直しを断行しました。物価下落(デフレ)を理由に、2013〜2015年度の3年間で最大10%以上の減額が行われました。
減額理由と政府の主張:
- 総務省「消費者物価指数(CPI)」が低下していた
- 一般国民との「公平性」や「モラルハザード」を防ぐ必要
しかし、現実は──
専門家や自治体からは、「物価下落を理由にしているが、実際には低所得者の生活必需品は値下がりしていない」との声が続出。特に食料品や光熱費はむしろ上昇傾向にあり、生活実態と制度の乖離が指摘されました。
この政策変更は一部の市民運動を活発化させ、各地で「生活保護基準の引き下げは生存権の侵害である」として訴訟が相次ぎました。自治体の福祉現場でも混乱が生じ、福祉事務所には相談者が殺到し、職員の対応が追いつかないケースも発生。福祉行政の現場を疲弊させる結果ともなりました。
2. 最高裁「引き下げは違法」──歴史的判決の内容とは?
2025年6月21日、最高裁第三小法廷は、生活保護費引き下げに異議を唱えた原告団(大阪府の母子家庭など)による訴訟で、国の処分を違法と認定しました。
判決の要点:
- 国が物価指数の適用に際して「不適切な算定方式」を用いた
- 実際の低所得者の消費構造を反映していなかった
- 政治的判断が先行し、科学的根拠に欠けていた
この判決は、行政の裁量権が無制限ではなく、統計的・社会的根拠に基づいた政策決定が必要であるという、憲法25条「生存権」の保障に関わる重要な判断として歴史に刻まれました。全国で係争中の類似訴訟にも波及する見通しであり、政府にとって極めて重い司法からのメッセージと受け止められています。
3. 追加支給は実現するのか?政府の動きと制度設計
厚生労働省は判決を受けて即座に対応を開始。27日の発表によれば、以下のような流れが想定されています。
現在の対応方針:
- 減額対象者に対し、差額分を追加支給する方向で検討
- 原告以外の受給者にも対象を広げる意向
- 立法措置(特別法または予算措置)が必要
- 財源規模は最大数千億円と試算
財源確保と制度整備の課題:
| 項目 | 検討内容 |
|---|---|
| 法案提出 | 臨時国会または通常国会で審議予定(秋以降) |
| 支給対象 | 原告含む約160万世帯に及ぶ可能性 |
| 支給時期 | 2026年度前半を目標とする見通し |
| 財源 | 補正予算、または特例公債の活用も検討中 |
現時点では、具体的な支給方法や手続きは未定ですが、自治体に再計算と支給通知の業務が課される見込みで、行政負担が増すことも想定されます。また、年金や障害者福祉制度との整合性調整も同時に進められるべきだとの指摘も強まっています。
4. 専門家の声──制度の「抜本的見直し」へ
● 岩田正美(社会保障学者/元日本女子大学教授)
「生活保護は“国民の権利”であり、過去の誤りを正すだけではなく、制度全体の透明性と科学的根拠を再構築すべきだ。」
● 小久保敦(弁護士/生活保護裁判弁護団)
「国が意図的に低く見積もった統計を基に政策を運用していた事実は極めて重大。生活保護だけでなく年金・医療など他の社会保障にも影響が及ぶ可能性がある。」
● 杉田容子(立命館大学教授/社会政策)
「生活保護は“最後の砦”であるべき。今回の判決をきっかけに、受給者を社会の一員として包摂する福祉政策へ転換を図るべきだ。」
専門家らは、生活保護が「恥」や「自己責任」といった社会的偏見と結びついてきた歴史を反省し、受給のハードルを下げ、制度利用者の尊厳を守る改革が必要だと訴えています。
5. 非受給者への影響と税負担の行方
今回の追加支給は、直接的には生活保護受給者を対象とするものですが、その財源には税金が使われることから、非受給者にも少なからぬ影響があります。ただし現段階では、補正予算や既存予算の再配分によって賄う案が有力であり、短期的な増税は想定されていません。
しかし中長期的には、社会保障全体の給付と負担のバランス見直しが求められ、消費税や所得税の見直し議論にもつながる可能性があります。特に高齢化が進む中、他の福祉分野との“予算の取り合い”が激化することも予想されます。
さらに、この判決を契機として「生活保障の最低ライン」が再定義される可能性も出てきました。最低賃金や住民税の非課税限度額、ひとり親家庭や障害者への手当など、多くの制度が生活保護基準に連動しており、今回の判決は広範な制度設計に波及する可能性を秘めています。
📊【図表①】生活保護追加支給が与える影響の構図(受給者・非受給者別)
| 対象層 | 影響の種類 | 具体的内容 |
| 生活保護受給者 | ①減額分の返還②信頼回復 | ・2013〜2015年の減額分を追加支給・制度への信頼性向上 |
| 非受給者(国民全体) | ①財政への影響②社会的連鎖効果③心理的安心感 | ・一時的な財政支出増・最低賃金・各種手当の見直しへ波及・将来の“万が一”への安心感 |
…
まとめ:違法判決を「未来の制度改善」につなげられるか
厚労省が動き出した「追加支給」は第一歩にすぎません。本質的な課題は、制度の信頼性と透明性をいかに担保し、必要な人に支援が届く仕組みを構築するかという点にあります。
また、社会のなかで「自己責任」という価値観が広がる中、生活困窮者に対するまなざしをどう変えるかも問われています。貧困は個人の責任ではなく、構造的問題として理解される必要があります。制度改善の動きが社会全体の価値観の転換を促すような契機となることを願いたいところです。
政治の場でこの問題がどう扱われるのか、今後の国会審議に注目が集まります。
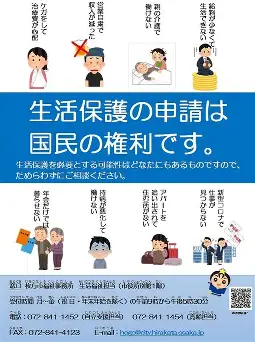


コメント