👋 はじめに

出典 jikayosha.jp
「サンキューハザード」や「パッシング」は、ドライバー同士の“ちょっとしたコミュニケーション”として日本では広く使われています。
でもその一方で、これらは正式な交通ルール上の合図ではないため、使い方を誤ると「ありがとう」のつもりが「危険の知らせ?」と受け取られてしまうことも。
そこで今回は、以下の4つのテーマを深掘りしてブログを再構成しました:
- ✅ サンキューハザード早見表
- ✅ パッシング早見表
- 🌟 譲り合いの基本マインド
- 🎯 まとめ運転中によく使う「サンキューハザード」や「パッシング」。実は誤解されやすく、トラブルにつながることも!?この記事では、安全に使える場面と控えた方がいい場面を深掘りして解説!譲り合いマナーを理解すれば、安心してドライブが楽しめます。
運転する方が“今すぐ実践できる安全マナー”として読んでいただける内容です。
✅ サンキューハザード早見表:感謝を伝える小さなサイン
「サンキューハザード」は、譲ってもらったときの“ありがとう”を示すお礼の合図として浸透しています。ですが本来は非常点滅表示灯=危険を知らせるサインです。使い方を誤ると誤解を招く可能性があります。
| シーン | 使ってOK | 控えた方がいい |
|---|---|---|
| 高速道路での合流直後 | ◯ 短く2〜3回点滅。後続車も余裕を持って認識できる | × 車間が詰まっていると「故障車?」と誤解されやすい |
| 渋滞中の車線変更 | ◯ 周囲が低速なので感謝の意思表示が伝わりやすい | × 雨や夜間で視認性が悪いときは混乱の元になる |
| 狭い道や駐車場 | ◯ 周囲の車が少なく、感謝が素直に伝わる | × 交差点直後で他車が多い状況では避けるべき |
💡 深掘りポイント:
- 回数は短めが鉄則。2〜3回で十分。
- 無理に使う必要はなく、軽く会釈や片手を上げるだけでもOK。
- 高速道路や悪天候では特に誤解を招きやすいため、状況判断が重要です。
✅ パッシング早見表:本来は危険を知らせる合図

出典 showono.com
「パッシング」はライトを点滅させることで意思を伝える方法ですが、本来の意味は**“危険を知らせる”や“ライトが眩しい”という合図**。日常的に「どうぞ」の意味で使われることもありますが、これは誤解や事故のリスクがあります。
| シーン | 使ってOK | 控えた方がいい |
| 夜間、対向車のライトが眩しいとき | ◯ 「ライトを下げてください」の合図として活用可能 | × 交差点で「どうぞ」の意味で使うと誤解の危険大 |
| 見通しの悪いカーブや狭い道 | ◯ 「ここに車がいるよ」と存在を知らせる目的で有効 | × 信号や警察官が交通整理している場所では不要 |
| 高速道路で前方に危険があるとき | ◯ 渋滞末尾や落下物を後続に知らせられる | × 自分が譲ろうとして周囲確認が不十分なとき |
💡 深掘りポイント:
- パッシングは「譲ります」ではなく「注意して!」の意味で使うのが正解。
- 譲りたい場合は、減速・停止という“行動”で示す方が安全です。
- 交差点など複雑な場面では使用を避けた方がトラブル回避につながります。
🌟 譲り合いの基本マインド:合図よりも大事なこと
- 「ありがとう」は必ずしも合図でなくてもOK。笑顔や軽い会釈で十分伝わる。
- 合図を出しても「相手が必ず理解してくれる」とは限らない。だからこそ、相手に依存しない安全確認が大切。
- 合図に頼りすぎず、ブレーキや減速など実際の運転行動で意思を伝えるのが最も確実。
- 感謝や意思表示よりも「安全運転を優先する」ことが結果的に周囲への思いやりにつながります。
💡 深掘りポイント:譲るときは「自分が完全に止まって相手が安全に動ける環境」を作ること。譲られる側も「合図に甘えず、自分で安全確認をして進む」姿勢が不可欠です。
🎯 まとめ:合図は便利だけど、過信は禁物

出典 car-moby.jp
「サンキューハザード」や「パッシング」はドライバー同士の温かいコミュニケーションの一環ですが、正式な交通ルールの合図ではないという事実を忘れてはいけません。
- サンキューハザードは“ありがとう”の気持ちを伝えるために、短く・シンプルに。
- パッシングは“注意喚起”に限定し、「どうぞ」の合図には使わない。
- 合図以上に大事なのは、安全確認と譲り合いの姿勢です。
次にハンドルを握るとき、この記事のポイントを少し意識するだけで、運転はもっと安心で気持ちの良いものになります。
帰省ラッシュでも日常のドライブでも、合図をきっかけに“思いやりドライブ”を広げていきましょう! 🚙💨


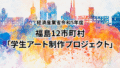

コメント