こんにちは。今回は、日本社会における「年功序列」と「成果主義」をテーマに、学生、新入社員、社会一般の意識の違いを整理し、その背景や企業・政策への示唆についてまとめました。
1. 年功序列と成果主義とは?
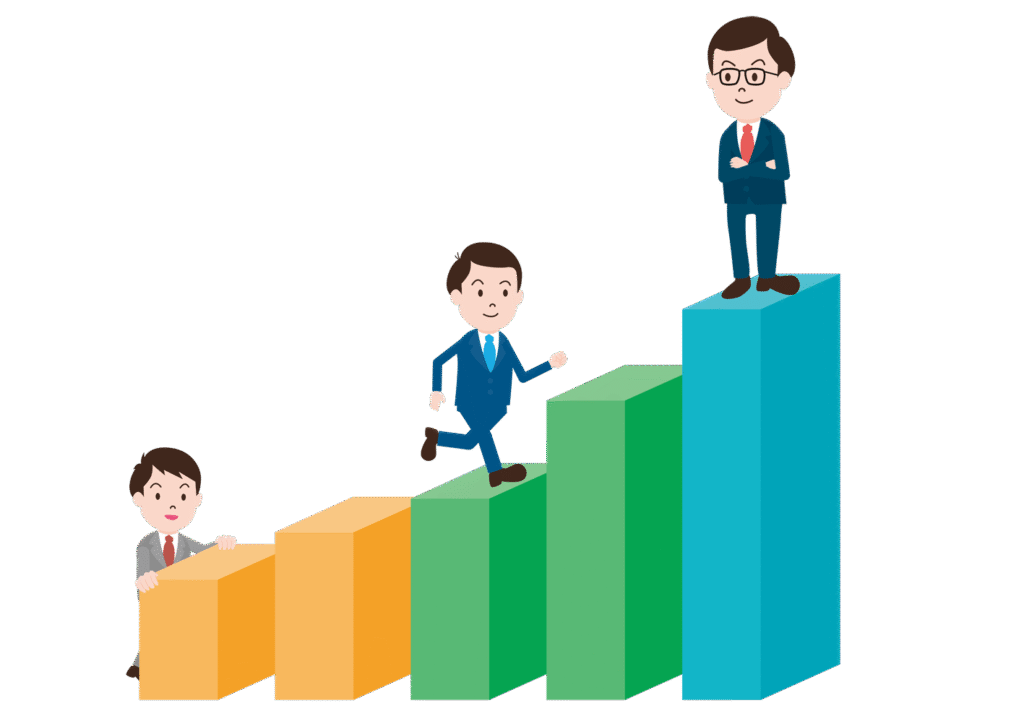
まずは基本的な定義を確認します。
| 項目 | 年功序列型 | 成果主義型 |
|---|---|---|
| 評価基準 | 勤続年数、年齢、経験 | 成果、能力、業績 |
| メリット | 安定性、公平感、長期的育成 | 努力が報われやすい、能力発揮の場がある |
| デメリット | 若手が不利、実力差が反映されにくい | 評価が不透明、精神的負担が大きい |
この二つは対立軸として語られがちですが、実際の日本企業は両者を組み合わせて運用することが多いです。
2. 学生(就活生)の意識
学生はどのように考えているのでしょうか?調査結果によると、多くの学生は「成果主義」に魅力を感じています。
| 調査対象 | 回答結果 |
| 「成果主義に魅力を感じる」 | 約25% |
| 「やや成果主義に魅力を感じる」 | 約43% |
| 合計 | 約68%が成果主義を支持 |
学生が成果主義を支持する理由
- 能力や努力が正当に評価されたい
- 転職前提の時代に合理的である
- 会社全体の生産性向上につながる
このように、学生は「挑戦」と「正当な評価」を求める傾向が強いです。
3. 新入社員の意識

一方で、実際に社会に出た新入社員の意識はどうでしょうか。2025年度の産業能率大学総合研究所の調査では、以下のような結果となりました。
| 選択肢 | 回答割合 |
| 年功序列 | 14.6% |
| どちらかといえば年功序列 | 41.7% |
| 成果主義 | 6.5% |
| どちらかといえば成果主義 | 37.1% |
合計結果: 年功序列派 56.3% > 成果主義派 43.6%
この結果は過去36回の調査で初めて「年功序列」が成果主義を上回ったことを意味します。
新入社員が年功序列を支持する理由
- 物価高や賃金停滞による将来不安
- 成果主義の曖昧さや評価の不透明感
- ワークライフバランスを重視するZ世代の価値観
つまり、学生時代の理想と、社会人になってからの現実には大きなギャップがあるのです。
4. 社会全体の実感
社会人全般に目を向けると、「成果主義」と「年功序列」が混在している現実があります。
| 表向きの制度 | 実態 |
| 成果主義 | 実際は年齢や勤続年数の影響が強く、年功的要素が残る |
「制度は成果主義を掲げているが、実際には年功序列の要素が濃い」という声が多く聞かれます。つまり、完全な成果主義は根付いておらず、混在型の制度が主流となっているのです。
5. 世代別意識の比較表
これまでの調査を基に、世代ごとの意識を整理しました。
| 世代 | 志向 | 背景 |
| 学生(就活生) | 成果主義志向(約60〜70%) | 正当に評価されたい/転職前提/能力発揮への期待 |
| 新入社員(2025年度) | 年功序列派が過半数(56.3%) | 経済不安/評価不信/安定志向 |
| 社会人一般 | 混在型 | 制度と実態の乖離、両立的運用 |
6. 企業への示唆
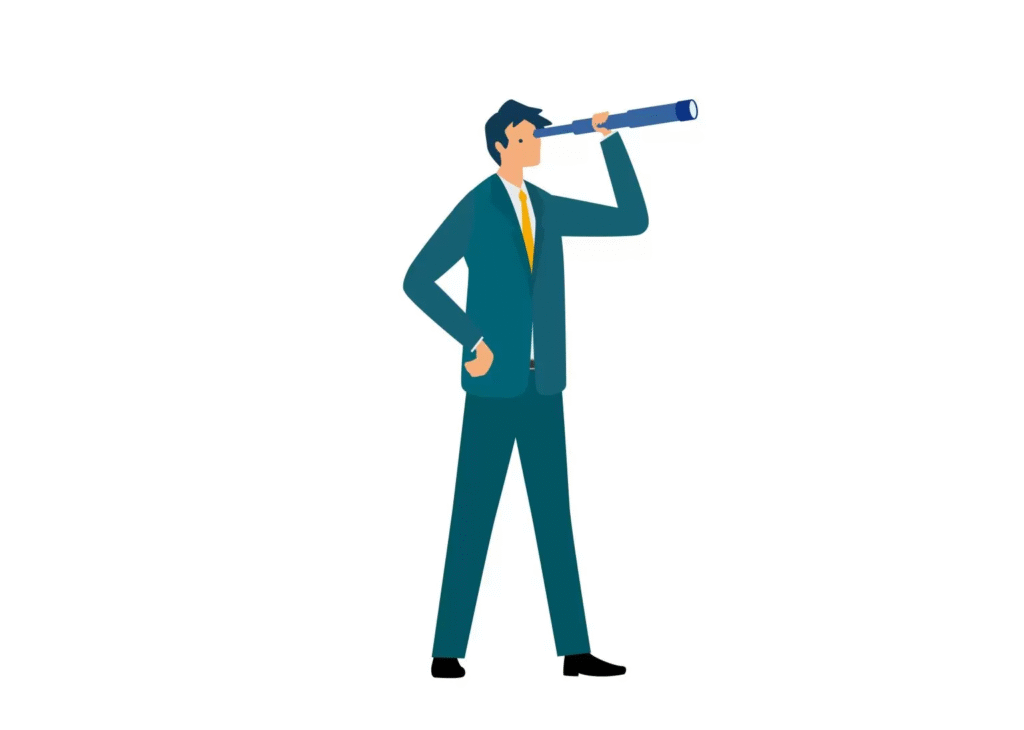
採用戦略
- 学生向けには「成果が正当に評価される制度」をアピールすることが有効です。
- 新入社員には「安心して長く働ける制度」を強調することが求められます。
人事制度設計
- 完全な成果主義や年功序列ではなく、ハイブリッド型が現実的です。
- 例:基本給は年功的に安定させつつ、賞与や昇進で成果を反映。
- 評価基準の透明化が信頼につながります。
7. 政策的な示唆
政府の「構造的賃上げ」方針や働き方改革の文脈でも、このテーマは重要です。
| 政策的課題 | 必要な方向性 |
| 賃金の伸び悩み | 安定を支える制度と成果反映の両立 |
| 雇用慣行の多様化 | ジョブ型(職務給)とメンバーシップ型(長期雇用)の折衷 |
| 若者支援 | 安定と挑戦を両立する仕組みの整備 |
8. まとめ

出典 saiyo.employment.en-japan.com
- 学生は 成果主義を理想視 します。
- 新入社員は 安定を求め年功序列を支持 する傾向が強まっています。
- 社会全体は 成果と年功の折衷で運用 しているのが実態です。
👉 今後、日本企業が現実的に取り入れるべきは「ハイブリッド型」人事制度です。学生や若手の理想と、社会人としての現実、そして企業の持続性をバランスさせることが、これからの大きな課題となります。
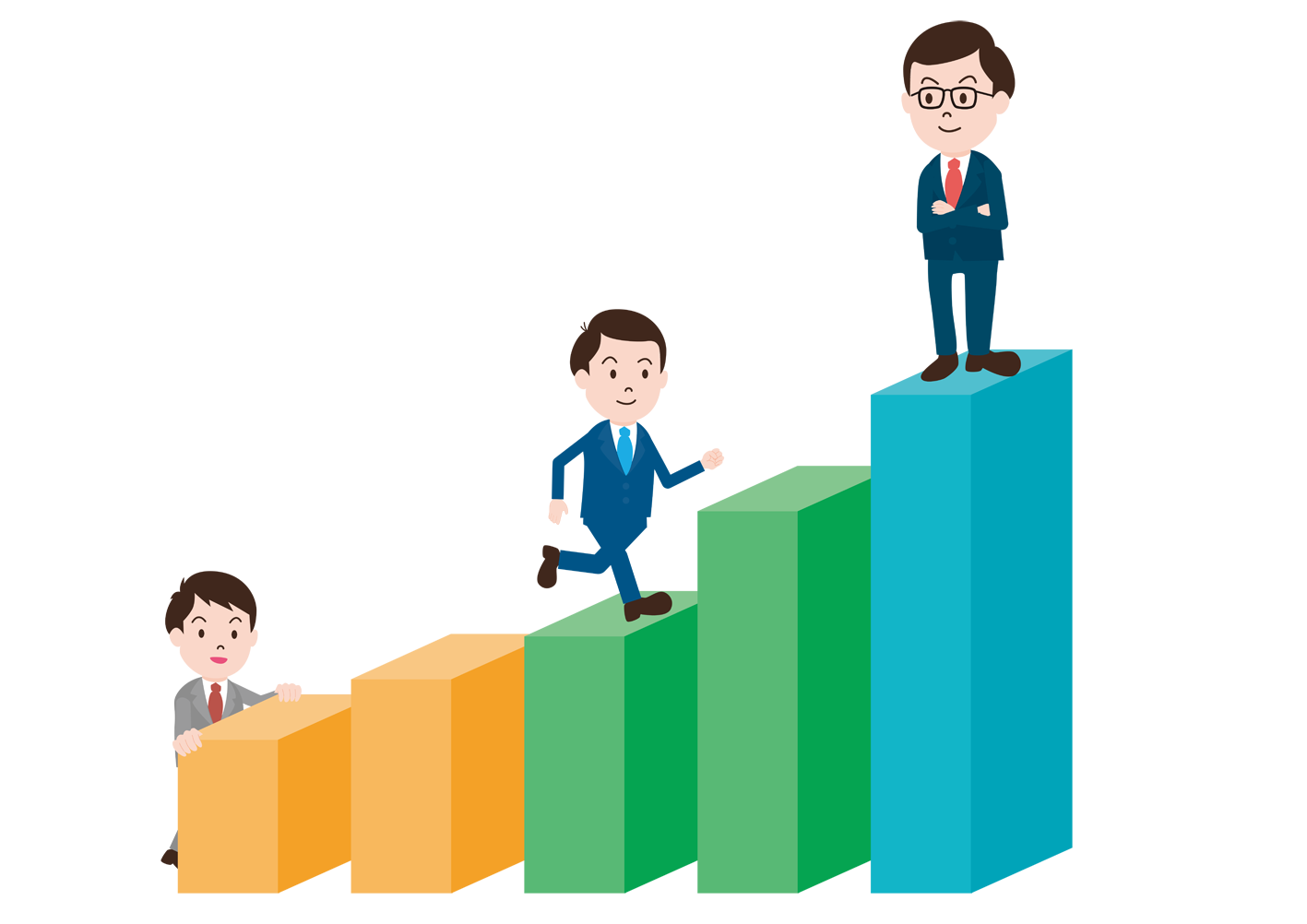


コメント