■ 「消費税をやめると円安になって物価が上がる」ってどういうこと?
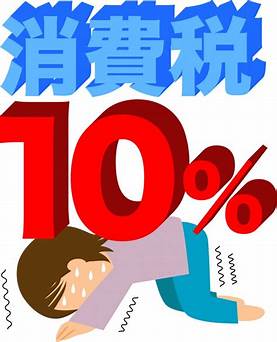
2025年5月、自民党の小野寺五典政調会長がテレビ番組でこう発言しました。
「消費税をやめるとか、いっぱいお金を配るとか、この原資を国の借金にした場合、円の評価が下がって円安、円安になるとまた買ってくるモノの値段が上がりますから、物価高になります」
この発言を聞いて、「え?減税って生活が楽になるんじゃないの?」と感じた人も多いはずです。
そもそも、消費税がなくなれば、スーパーでの買い物や電気代の請求額も下がる。それだけで家計の負担はかなり軽くなります。
でも政治家は「減税は危険だ」と言います。なぜ、私たちの生活よりも、「国の借金」や「円の価値」が重視されてしまうのでしょうか?
■ 消費税が生活に与えるインパクトはどれくらい?
日本の消費税は現在 10%(食品などは軽減税率で8%)。この「10%」は、一見すると小さく見えるかもしれません。でも、毎日の生活にかかるお金すべてに税がかかっていると考えると、負担の大きさが見えてきます。
たとえば──
- 月の食費が8万円 → 8%の税で 約6,400円
- 日用品や家電、外食費など月5万円 → 10%の税で 5,000円
- 1年間で単純計算しても 10万円以上の税負担が発生します
もしこれがゼロ、あるいは5%に下がったら?
家計には確実に「ゆとり」が生まれます。将来に不安を抱える人が多い今、目の前の生活を軽くすることの意味はとても大きいはずです。
■ 政府が減税に慎重な3つの理由

小野寺氏だけでなく、自民党や財務省には「減税は慎重に」という空気が広がっています。その背景には主に3つの理由があります。
① 「借金=悪」という強い思い込み
日本の国の借金(国債残高)は約1,200兆円以上。これだけを見れば確かに不安に感じるかもしれません。
政治家たちは「これ以上借金を増やしたら、将来世代にツケが回る」と言います。でも、その一方で大企業への補助金や、防衛費の増額には積極的です。2025年度の防衛費は過去最大の約8兆円にのぼる見込み。
なぜ「借金が増える」と言いながら、生活支援だけを我慢させるのでしょうか?
② 円安の原因を「国民のせい」にしていない?
小野寺氏の発言では、「減税=借金増加=円安進行=物価高」という流れが前提になっています。
でも、本当にそうでしょうか?
円安の最大の原因は、日米の金利差です。アメリカが金利を上げ、日本が低金利を続けていることで、世界中の投資家が円を売ってドルを買っているのです。
つまり、「日本政府の財政支出」だけが円安の原因ではありません。
それを無理やり「減税は円安につながるからダメ」とするのは、国民に責任を転嫁しているようにも感じられます。
③ 減税が「人気取り」に見えるという偏見
「減税」や「給付金」という言葉に対し、自民党内には「バラマキ」「ポピュリズム(大衆迎合)」といった否定的な印象を持つ人が多いようです。
でも、世界を見るとどうでしょう?
- ドイツは2020年、消費税にあたる付加価値税を 19%→16%に引き下げ
- イギリスは飲食業へのVAT(付加価値税)を 20%→5%に一時的に引き下げ
どちらも家計の負担軽減と景気回復を目的に、思い切った減税を実施しました。
なぜ日本では、それが「悪いこと」のように扱われるのでしょうか?
■ 「財政よりも生活」を優先してほしい
たしかに、国の財政も大切です。でも、私たちは毎日の買い物、光熱費、家賃、教育費などの支払いに苦労しています。
ガソリン代は1リットル170円台、食品は次々と値上げ、電気代も前年より2割以上高くなった家庭もあります。
生活の苦しさは、数字ではなく「実感」として迫ってきています。
それなのに、政治家たちが言うのは「財政規律が大事」「円の評価が下がると大変」──。
私たちが求めているのは、未来の理屈よりも「今の安心」なのではないでしょうか?
■ 政治を変えるのは「私たちの声」
「減税したら物価高になる」と言われても、納得できないのは当然です。
政治や経済が難しくても、「この生活のままではしんどい」「少しでも支援してほしい」という感覚は、すべての人が持つリアルな声です。
そして、その声を届ける方法が「選挙」であり、「世論」です。
政府が何を優先すべきかを決めるのは、私たちの声と行動なのです。
■ 最後に──「当たり前の暮らし」を守る政治を求めて

「物価が上がっても税金は変わらない」「給料は増えないのに出費だけ増える」──そんな状況に慣れてしまっていませんか?
私たちが当たり前に感じている「苦しい生活」は、決して当たり前ではありません。
政治のあり方次第で、もっと暮らしやすい社会はつくれるはずです。
だからこそ、「消費税をやめたら円安で物価高になる」というような一方的な説明に対しては、しっかりと疑問を持ちたい。
そして、「今の生活を少しでも楽にしてほしい」という声を、遠慮せずにあげていきましょう。


コメント