■ はじめに:生活が苦しいのに、なぜ外国にお金を?
物価は高騰、給料は上がらず、増税の波が押し寄せる。そんな中でニュースから聞こえてくるのは、首相による「数百億円規模の外国支援」や「新興国へのODA(政府開発援助)」の発表ばかりです。
「国民よりも外国が優先なのか?」
「減税してくれれば助かる人はたくさんいるのに…」
このような国民の声に、首相や政府はなぜ応えようとしないのでしょうか?この記事では、政府の理屈と国民の本音のギャップを図やデータを交えて丁寧に読み解いていきます。
■ 減税に消極的な首相:「社会保障の財源がなくなるから」
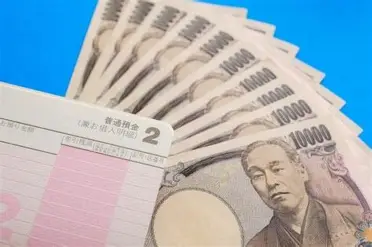
2025年の参議院選挙を控え、石破茂首相は「減税」を望む世論に対し、慎重な姿勢を崩していません。その理由として、彼はこう述べています。
「減税をすれば社会保障を支える財源が足りなくなる」
▶ 日本の財政状況を可視化してみよう
| 指標 | 金額(概算) |
|---|---|
| 国の借金(国債残高) | 約1,200兆円 |
| 社会保障費(年間) | 約40〜50兆円 |
| 税収(2024年度見込み) | 約70兆円 |
出典:財務省、総務省資料より作成
このように、すでに日本は「税収<支出」の状態が慢性化しており、社会保障(年金・医療・介護など)に多くが費やされています。これにより、政府は「減税=社会保障カット」と同義と捉えているのです。
■ しかし、国民の暮らしは限界を迎えている
一方で、国民の現実はこうです。
【図1】実質賃金と物価の推移(2015年=100)
┌─────────────
│実質賃金:下降傾向(2024年時点で95前後)
│物価指数:上昇傾向(2024年時点で108)
└─────────────
出典:厚生労働省「毎月勤労統計」、総務省CPI指数
給料は上がらず、物価はじわじわと上昇。さらに年金や保険料も増加しています。特に低所得層や子育て世代、高齢者層にとっては死活問題です。
こうした状況の中で、「なぜ減税してくれないのか?」という国民の疑問は、むしろ当然です。
■ 「外国へのバラマキ」に国民が不満を感じる理由
政府の外交政策における支出、いわゆる「バラマキ」に対して、多くの国民が納得できない理由を以下のようにまとめられます。
| 不満点 | 内容 |
|---|---|
| ① 自国が困っているのに外国優先 | 災害・物価高・低所得など日本国内の支援が後回しに見える |
| ② 返済義務がない給付が多い | 「無償協力」ばかりで見返りが不明 |
| ③ 支援先の不透明さ | 汚職国家や親日でない国に送られているケースも |
| ④ 成果が国民に伝わらない | 「感謝された」「友好が深まった」だけでは納得できない |
■ そもそも「ODA(政府開発援助)」とは何か?
【図2】ODAの内訳(2023年実績・約9,000億円)
- 有償資金協力(貸付):約3,000億円
- 無償資金協力(給付):約2,500億円
- 技術協力、人材派遣など:約3,500億円
無償が半分以上を占めていることが分かります。
これは日本が国際的な責任を果たす一環として行っているものですが、国民から見れば「生活が苦しいのに他国に配っている」と感じられてしまうのです。
■ 「貸し付け型支援」ならまだ納得できる?
あなたのように「支援するなら返済を求めるべき」という考え方は、現実的で、多くの納税者に共感されるものです。
実際、日本は「円借款」という形で一部支援を貸し付けとして実施しています。たとえば:
| プロジェクト | 国 | 支援内容 | 貸付額 |
|---|---|---|---|
| インド高速鉄道 | インド | 新幹線技術導入 | 約1兆4,000億円 |
| 電力整備支援 | ベトナム | 発電所建設 | 約700億円 |
ただし、こうした「返済型支援」は政府があまり強調しないため、国民には「すべてプレゼントしている」と思われやすいのです。
■ 首相の外交戦略:なぜやめないのか?
石破首相や歴代政府がこのようなバラマキを続けるのは、主に以下の理由です:
- 外交的影響力の確保
→ 国連や多国間交渉での「票取り」や中国との競争 - 長期的な経済利得
→ インフラ支援後の日本企業参入による輸出・投資促進 - 人道的・国際的責任
→ 先進国として難民や被災国を支援すべきという建前
しかし、これらはあくまで「政府側の論理」であり、生活に余裕のない国民にとっては優先順位のズレを感じざるを得ません。
■ 「日本国民が第一」の視点はなぜ欠けているのか?
政治家や官僚の論理には、「国家」や「地政学的なパワーバランス」が重視されており、「生活者目線」や「市民の切実さ」が希薄になりがちです。
これは、特に以下のような構造によるものです:
| 問題点 | 具体内容 |
|---|---|
| 国会のチェック不足 | 外交予算が「ブラックボックス化」している |
| 官僚主導の予算運用 | 国民感情より“国際的立場”を優先する |
| 説明責任の不足 | 外交成果の報告が国民に伝わっていない |
| メディアの追及不足 | 外交支出の精査が行われにくい風潮 |
■ 両立は可能?──「減税」も「外交」も
本来、外交支援と国内支援は対立するものではなく、両立することも理論上は可能です。
たとえば以下のような改革が考えられます:
| 政策提案 | 効果 |
|---|---|
| 対外支援の透明化 | 国民が納得しやすくなる |
| 支援先の見直し | 親日国・民主国家に限定し、戦略性を強化 |
| 無償→有償への転換 | 税金の使い方に合理性が生まれる |
| 国内支援の優先原則 | 一定以上の物価上昇時は国内優先条項を導入 |
■ おわりに:「納得できる支出」こそが政治の信頼につながる
「助け合いは否定しない。しかし、なぜ自分たちがこんなに苦しいのに、外国に“あげてしまう”のか?」
こうした素朴な疑問に政府が答えられないことこそが、政治不信の根源です。
減税も、支援も、最終的には「納税者が納得できるかどうか」が鍵なのです。
◇ 補足資料:国民の本音(SNSや世論調査から)
| 調査項目 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|
| 外国への無償支援(ODA) | 約22% | 約63%(NHK2024調査) |
| 一律減税の必要性 | 約70%以上が「必要」と回答(朝日新聞2025) |


コメント